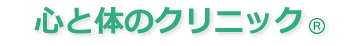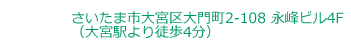うつ病・うつ状態
当クリニックを受診する患者さんの傾向
以下は当クリニックを受診するうつ病(うつ状態)患者さんの傾向(特徴)というよりは、主要駅の近いビル診療所に受診する患者さんの傾向と考えてください。
うつ病に限らず、心療内科の多くの病気は原因別にストレスタイプ、心因タイプ、内因タイプ(内因性)に大別できますので、ここではタイプ別での傾向を述べておきましょう。
まずストレスタイプです。これは当クリニックに受診するうつ病(うつ状態)のなかでは一番多く、半数以上を占めます。
これらは元々は健康だったのに、ストレスのためにうつ状態になる例です。ストレスの原因として多いのは男性は残業やノルマ、パワハラなど、仕事がらみです。女性で多いのは職場や家庭などの人間関係のトラブルです。
次に多いのは心因タイプです。もともと対人関係が苦手だったり職場環境に馴染みにくいといった性格傾向に加えて、環境要因のため悩みがちになったり投げやりになりうつ状態になる例です。
ストレスもなく、性格的要因もなく、原因がはっきりかないのにうつ状態になる例(内因性)もあります。このタイプは全体の一割以下です。この中には季節などによって周期的に悪化する例や、ときどき軽い躁状態にもなる双極性障害2型なども含まれます。
抗うつ剤の特徴と副作用
- 抗うつ剤はSSRI、三環系抗うう剤、三環系抗うう剤、SNRI、NaSSAなどに分類されます
- ルボックス/デプロメール(フルボキサミン)
- パキシル(パロキセチン)
- ジェイゾロフト(サートラリン)
- レクサブロ(エクシタロプラム)
〔○SSRI〕
SSRIの特徴
ルボックス/ デプロメール(1999年)、 パキシル(2000年)が日本に登場してから、副作用が少ないという評判もあり2000年~2010年頃はどこのクリニックに行ってもSSRIが処方されると言われるほどになった。現在でも心療内科で出される抗うつ剤の半数以上がこの系統の薬です。
SSRIの副作用
副作用が少ないという前評判でしたが、実際は服用開始して数日間は吐き気や眠気がでやすい。副作用が一週間以上続くようなら他の薬に変えることも検討した方がよいでしょう。
これとは別に長期間、薬を服用していて、突然服用を中断すると三日目ぐらいに不眠や、体のしびれ、吐き気などが起こる(退薬症候群)可能性があります。この場合、一錠でも服用すると症状は改善する場合が多いです。SSRIに限らず抗うつ剤は自己判断で急に中断しないことが大切です。
〔○三環系抗うつ剤〕
三環系抗うつ剤の特徴
SSRIが発売されてからは、使用頻度がぐっと減ったのですが、重症のうつやSSRIで無効例でも効果があることもあり、今も使われています。なお三環系抗うつ剤のアモキサン(アモキサピン)は2022年に販売中止になりました。
三環系抗うつ剤の副作用
口渇、便秘、ねむけ、ふらつきなどの副作用が出やすい。
〔○四環系抗うつ剤〕
四環系抗うつ剤の特徴・副作用
老人のうつによいとされている。夜に服用しても朝眠気が残ることが多く、逆に夜中に目覚めてしまう不眠症に使うこともある。
〔○SNRI〕
SNRIの特徴
SSRIと三環系抗うつ剤を合わせたような薬。このうちトレドミンは2000年に発売されたが、副作用が少ないが効果も弱いとされあまり使われなかった。SNRIがよく使われるようになったのはサインバルタ(2010年)が発売されてからである。
SSRIより早く、一週間前後で効果でやすいという魅力がある。
SNRIの副作用
SSRIと三環系抗うつ剤のどちらにも似た副作用も出ることがある。SSRIより副作用が出やすい印象がある。
〔○NaSSA〕
NaSSAの特徴
四環系抗うつ剤テトラミドの改良型。一週間程度で効果が出る。不眠を伴う軽症のうつに使いやすい。
NaSSAの副作用
眠気がでやすい。特に初めて服用した翌日は眠気が残りやすい。
〔○その他〕
- トリンテックス(ボクチオキセチン)
- レスリン/デジレル(トラゾドン)
- ドグマチール(スルピリド)
- エビリファイ(アリピプラゾール)
- デパケン(パブプロ酸)
多様化するうつ病の治療薬
 2000年、うつ病治療の主役交代。三環系抗うつ剤からSSRIに
2000年、うつ病治療の主役交代。三環系抗うつ剤からSSRIに
うつ病(うつ状態)に処方される治療薬の変遷を簡単に触れます。
うつ病の治療薬は、二十一世紀を迎えるころに大きな節目がありました。それまでトフラニール(1959年発売)、トリプタノール(1961年)、アモキサンといった三環系抗うつ剤が主流だったのですが、ルボックス(1999年)やパキシル(2000年)といったSSRIが登場してからうつ病治療薬の主役が交代しました。
このため一時期は「どこのクリニックを受診しても出される薬はSSRI」といった極端な状態にすらなりました。なぜ、そんなことになったからいうと当時、「うつ病の原因はセロトニンの不足だ」という説が幅を利かせたからです。
もともとうつ病の原因は、脳内の神経(シナプス)同士を繋ぐ役割をする神経伝達物質、モノアミン(注1)の不足が原因だとする仮説があり、この時期にはモノアミンの一つであるセロトニンが脚光を浴びたのです。
ところが神経伝達物質の動きは現在の科学では直接、知ることができないため、それは一つ仮説でしかありません。
実際その当時から「うつ病の原因はセロトニンだけではない」という研究者の意見や「(昔からあったセロトニンとは直接関係のない)三環系抗うつ剤の方が効果的なケースも少なくない」という医者もいたのですが、少数派の意見という扱いでした。
 SNRIの登場で多様化へ
SNRIの登場で多様化へ
この流れが変わったのはSNRI、サインバルタ(2010年)の登場でしょう。
これは簡単に言うとセロトニンに加えて、従来の三環系抗うつ剤にもあったノルアドレナリンを増やす効果を狙ったものです。実際にSSRIが無効だった人で、SNRIに変えてみたら効果的だったという例も見られることから「どうやらセロトニン仮説は絶対ではなさそうだ」と考える医者が増えました。
ではうつ病の原因は、セロトニンとノルアドレナリンの二つかというと、それだけでもなさそうなのです。
たとえばセロクエル、エビリファイ、ジプレキサなど統合失調症に使われる向精神病薬も抗うつ剤と併用することで、抗うつ剤だけでは効果不十分な人が良くなるという報告も増えたのです。これらの薬は、快楽物質などとして知られるドーパミンと関係する薬です。
さらにこれに加え、今では従来てんかんに使われていた薬などもうつ病治療に使われるようになりました。これからも分かるように、うつ病の原因物質はまだ解明されていないというのが現状でしょう。
 抗うつ薬の選び方。再び、経験と知識が必要に
抗うつ薬の選び方。再び、経験と知識が必要に
原因物質の解明は研究者に任せるとして、このように治療薬の選択肢が増えた現状は患者さんにとってはプラスのはずです。しかし私たち治療にあたる医者にとっては大変な時代になったと私は考えています。
というのはSSRIが登場する以前、治療薬の選択は十分な臨床経験と知識が必要な仕事でした。それがSSRIが登場してから治療法がごくシンプルになり「どの医者が処方しても内容はほとんど同じ」というほどになりました。
しかし「うつ病の原因はセロトニン」という仮説に疑問が持たれるようになった今、再びうつ病の治療には、再び経験と知識が問われる時代になったからです。
おまけにこの間、ジェイゾロソト(SSRI、2006年)、レクサブロ(SSRI、2011年)、イフェクサー(SNRI、2015年)、リフレックス、レメロン(2009年)、トリンテックス(2019年)などの新しい薬も次々と発売され、それぞれ微妙な薬効の違いがあります。
私もうかうかしてはいられません・・・。
注1)モノアミンにはセロトニン、ノルアドレナリン、アドレナリン、ヒスタミン、ドーパミンがある。現在、セロトニンだけでなくモノアミン仮説そのものも疑問が呈されている。
うつ病と休職
 どんな状態になったら仕事を休むべきか?
どんな状態になったら仕事を休むべきか?
明らかな体調不良のときは仕事を休むしかないと誰でもわかります。しかし何とか働けてはいるが毎日が辛い。休むべきかどうか迷う、という場合もあるでしょう。そんなときはどうやって判断すべきでしょうか。以下の事柄を休むかどうかの一つの目印としてください。
まず職場です。仕事でミスが増える、段取りが悪くなる、会議で話の流れについてゆけない、ちょっとした頼まれ事や余分な仕事が負担に思える、職場仲間に「おかしい」などの指摘をされる。
次に家庭です。ふだん習慣のようになっていること、例えば寝る前にテレビを見る、休日に買い物に出かける、などができない。家族から「最近おかしい、会社を休んだ方がいい」などと勧められる。
もちろん自覚症状も重要です。中でも睡眠、食欲、便通などの生理的なことは大きな目安になります。まず睡眠です。うつ状態のときは中途覚醒(夜中に目覚める)、朝早く目覚めてしまう(早朝覚醒)ことが増えます。また食欲は、お腹が空いても食べたくない。食べても美味しくない状態になります。便通はウサギの糞のような便秘が多いのですが、下痢になることもあります。
この他にだるくて仕方がない、余分なことをやりたくない、やる気が出ない、イライラするなどの症状も出ます。ただし、症状は治療で改善する可能性もあるので、自覚症状だけで休職を急ぐ必要はないでしょう。
 どの位の期間、休むか?
どの位の期間、休むか?
休むとしても、ではどの程度休めばいいのか、という問題が出ます。
自分で「長くかかりそうだ」と長期間の休養を前提とした診断書を希望する人もいますが、特に初めてうつ状態になった人の場合は、最初から長く休むと決めてしまうことには賛成しません。
それというのも、たとえ重症に見えても家でゆっくりするだけでも急速に回復する人もいるからです。またあまり長い休職は職場復帰でつまずく可能性もあります。
逆に休職期間が短すぎると、まじめな人は職場のことが気になりゆっくり休めないという状態にもなります。したがって、休職期間は仕事内容や職場環境だけでなく、病状やその人の性格傾向などを含めて検討する必要があります。
ただ初診で受診する患者さんの多くは、仕事を続けるのが困難になって初めて受診するという例が多いのが実情です。この場合は初診時に、どの程度休むべきかを決める必要が出ます。
このためうつ病と診断したときは、患者さんと相談の上「当分の間、休養を要す」とか「一カ月間、休養を要す」といった表現で書くことが多くなります。
うつ病の場合は抗うつ剤が効果が出るのに二週間から一カ月かかるので、本来なら一カ月以上の休職期間がほしいところですが、休んだだけでよくなる場合も想定して、こうした表現の診断書になることが多くなります。
この場合、休職期間が切れる前にもう一度、もう少し休むべきかそれとも復帰すべきか、を相談することになります。
 どうなった時点で復職すべきか?
どうなった時点で復職すべきか?
うつ病に限らず、復職の時期やその方法は重要です。体調がせっかく回復したのに復職してすぐに再発するということも珍しくないからです。普通のサラリーマンの場合、復職できるかどうかの目印として、朝起きて夜寝るという生活が無理なくできている。昼間、何もしないと退屈だと感じ、何らかしらのことをやろうと思い、またやれている、などが目印になるでしょう。
また復職前にできれば実際に朝起きて、電車に乗り、会社の近くまで行って、夕方自宅に戻るという体験をしてみた方がよいでしょう。長期に休んだ場合、「会社に行くだけで疲る」と訴える人は多いものです。
また復帰後の職場環境も重要です。たとえば会社の人間関係でうつ状態になった人なら、同じ職場に戻ればまた悪化する可能性があります。したがって、休職している間に復職後の職場環境を検討し、場合によっては異動などを含めて職場と交渉して、職場復帰をしやすい環境作りをする必要があります。
さらに、職場に戻った初日から、復職前と同じだけ働くのは無理なので、仕事の負荷が少なくする工夫をすべきです。そのためには半日勤務や負担の少ない仕事に就ける配慮が望ましいところです。ただし、会社によっては、そうした要望が叶えられないことが多いのも実情です。
 薬はどうするか
薬はどうするか
薬を服用しなくて済む状態で職場に戻りたい、と話す人がいます。しかしそうでなくても職場復帰をしたばかりはストレスが溜まりやすい状態になりがちです。したがって職場復帰した当初は抗うつ剤の減量は避けるべきでしょう。
うつ病治療。運動と安静、どっちがいいの?
 どちらにも支持者がいるが・・・
どちらにも支持者がいるが・・・
うつ病(うつ状態)になった患者さんに対して、運動を勧めるべきか、それとも安静を勧めるべきかという議論があります。
世界的にみると、運動(運動療法)が効果あると考える医師は決して少数派ではありません。
たとえば英国国立医療技術評価機構 (NICE)の診療ガイドラインでは、軽中度のうつ病患者に対しては、認知行動療法と並んで運動療法を選択肢の一つとして推奨していますし、実際イギリスの総合診療医 (GP) の20%以上が抑うつ症状の患者に対して、しばしば運動療法を「処方」しているようです。またドイツでもうつ病に対して運動療法を勧めることはごく一般的という話を聞いたことがあります。
ただし日本では積極的に運動療法を勧める医者は少数派です。日本うつ病学会のガイドラインでも「うつ病に運動が有効だとする報告がある一方で、否定的な報告もあり、まだ確立された治療法とはいえない」といった慎重な表現をしています。
おそらく日本では運動よりも安静を勧める場合が多いと思われます。ただしうつ病に安静が有効だとする研究報告は(たぶん)ないでしょう。
私は、「どっちがいいのか」という議論自身に無理があるように思っています。連日の過酷な仕事で疲れ切った人に「運動」を勧めるのは酷なように思いますし、うつ状態が慢性化している人に「安静」を指示するのもどうかと思います。
 ヒントは絶対臥褥
ヒントは絶対臥褥
ではどうすればいいのでしょうか。私とて、結論めいたものはわかりませんが、そんなとき思い出すのは「絶対臥褥(ぜったいがじょく)」です。これは日本で生まれた精神療法の一つである森田療法において、入院治療で最初に行うものです。
絶対臥褥はトイレなどを除き個室で一週間、布団(ベッド)の上でひたすら過ごします。この間はテレビや読書、会話など、一切の気晴らし行為は禁止です。
この指示を言い渡されると、初めのうちは「寝ているだけなら楽だろう」と思った患者さんもそのうち、こんな毎日が苦痛になり、何かやりたくなってくる。森田療法ではそこを狙って、掃除などの簡単な作業をさせる、という次の治療段階(軽作業期)に進みます。
森田療法は森田神経質というタイプの患者さんに対する治療法なので、そのままうつ病の治療には当てはまりません。しかし、絶対臥褥は人間にあるもともとの特徴をうまく利用したものだと思います。それは「人は本来、何かをやりたくなるようにできている」という特徴です。
ヒトは動物、つまり動く存在、と分類されていますがその通りなんだと思います。
 答えは本人が知っている
答えは本人が知っている
人は動物なので、動くようにできていて、安静を続けることには苦痛を感じるようになっている。これはうつ病の人でも同じはずです。ですから初めは安静にするにしても、やがて飽きてきたり、苦痛を感じるようになったら、その気持を尊重して、何かを始めればいいのです。
それは掃除や趣味、化粧、おしゃれなど何でもいいのです。そして具体的な何かを思いつかないようなら、運動も試みる価値がある事柄の一つでしょう。
では、どの程度の運動が望ましいでしょうか。これは個人によって違います。たとえば高校生にとって散歩よりはジョギングの方がいいでしょうし、高齢者なら散歩の方がよいでしょう。
うつ病治療で重要な点は、運動か安静かという選択ではなく「元々その人に備わっているリズムを取り戻す」ことだと私は考えています。たとえばうつ病は夜中に目覚めてそのまま眠れなかったり(中途覚醒)、まだ暗いうちに目覚めてそのまま朝を迎えたり(早朝覚醒)しますが、これは睡眠のリズムが乱れた状態です。
またうつ病では食欲不振や便秘(下痢)などもよくみかけますが、これも食物摂取-消化-排泄といった一連のリズムの変調です。
ですから無理がない程度でこうしたリズムを取り戻す試みは、うつ病治療にはプラスになるはずです。「安静かそれとも運動か」という問題も、リズムを取り戻すにはどうすれば良いかという視点で議論すべき、というのが私なりの考えです。
退職うつ。こんなときどうするか
 退職うつとは?
退職うつとは?
退職うつ(退職うつ病)とは、長年多忙な生活を送っていた人が仕事から離れ、やっと楽になった、自分の好きなことができる、という本来なら願っていた毎日が実現したのにうつ状態になることです。
退職うつという言葉は正式な病名ではなく、あくまでうつ状態の一つです。しかし他のうつとちょっと違うのです。一般的にうつ病(状態)は、体質要因とでもいうべきうつ(内因性、双極2型など)と、ストレスなどによるうつ状態に大別できます。ところが退職うつは多忙でストレスフルな毎日がやっと終わった頃にやっくる「うつ」なのです。
退職うつは身を削るような日々が終わり、一休みしている状態とも違うのです。それだけならマラソンランナーがゴールに達したとき、疲労困憊しているように見えても、ちょっと休むと直ぐ回復するのと同じで、健康な反応です。ランナーの中には走り終わったその夜には打ち上げパーティーで陽気に騒ぐ人も珍しくないように、一休みというだけなら通常は長くても一カ月以内に元気になります。
ところが、退職したばかりの時期には、やりたいことが沢山あると思っていたり、実際何かに取り組んでいたのに、だんだん意欲が減退してうつ状態になる人がいるのです。これが退職うつです。
 退職うつ。どうすればよいか?
退職うつ。どうすればよいか?
こんな場合、どうすればいいのでしょうか。通常、うつの治療の基本は抗うつ剤の内服と休養です。とくに休養は大切なので、うつ病に対しては休職を勧めることが多いのです。ところが退職うつの場合は、仕事をしていないので本人さえその気になればいつでも休養はできるし、また実際「何もしないで、家でごろころしています」と答える人が大半です。
この人達は、何をしたらいいかが分からなくなっているのです。趣味や旅行、ボランティアなどアイデアとしてはあるのですが、どれもその気になれないのです。一番良いのは何も考えずに「試し」のつもりで何でもやってみるという態度を持つことでしょう。ただ気力が失せるとそう心がけるのも苦しくなります。
そんなときは、まずは規則正しい生活、適度な運動を、心がけてみてください。規則正しいというと、つい早寝早起き、決まった時間を運動するなどをイメージしがちですが、そこまでしなくても構いません。毎日だいたい同じ時間に寝て、同じ時間に寝る。そして同じ時間に食卓につくといったアバウトな規則正しさです。また運動も、ちょっと体をほぐす程度で十分です。
ではこれがどんな意味があるのでしょうか。退職うつの人は、頭でっかちになり、考えることに疲れているのです。こうなるといくら考えても良いアイデアが出る可能性はほとんどなく、ただ考えが堂々巡りしているだけになっています。
規則正しい生活を心がけると、時間になるととりあえず、考えが中断され、ささやかでも行動することになります。また生活が規則正しくなると、体のリズムも戻ってきます。
当たり前のことですが、退職うつの人は、ちょっと前まで健康だったのです。「自分は退職したのだ。何か次にやることを見つけなくては」とか「このままでは将来が不安だ。何かやらなくては」という自分で作ったプレッシャーから少しでも身軽になるだけで、元々の健康な自分に近づくのです。
もし、後悔や心配ばかりで、何もできなくなっているなら、こうした簡単なことから始めてみてください。
「怠ける試み」の勧め
うつ病に対して、さまざまな治療法があります。このうち薬物療法(抗うつ剤)が有効なことはデータが示しています。では抗うつ剤以外の治療はどうでしょうか。
これには静養(安静)、運動療法、認知行動療法などがあり、最近ではTMS(経頭蓋磁気刺激)などを勧める医師もいます。ただし、このうち運動療法や認知療法はうつ症状が本当に悪いときは行いにくいし、TMSは有効性がまだ明確でないというのが実情ではないでしょうか。
したがってうつ病になった場合は、薬物療法に加えて、まずは無理なことを避けて「静養」するのが無難でかつ有効な方法でしょう。
私はうつ病の人に「怠ける試み」を勧めることがあります。
それというのもただ「静養するように」と伝えても、人によっては「ずっと寝ていればいいのか」「散歩はいけないのか」「テレビやゲームなど、刺激になることは一切やってはいけないのか」などの疑問が次々に湧いて,どうすればよいか迷ってしまうことがあるからです。
うつ病のときに行う「静養」の目的の一つは体を休めて疲れを取ることです。うつ病は精神的な病気だと思われがちですが、肉体的にも疲弊していることが多く、疲労感や肩こり,頭重感、食欲不振、便通異常などの症状もよく出ます。これらの一部は体を休めるだけでも改善します。
「静養」のもう一つの目的は、不必要な思い込みをいったん中断することにあります。うつ病の人は、仕事や家事などを「しなくてはいけない」という気持にさいなまれやすい傾向があります。
その一方で体調も気力も不調になり、「しなくてはいけないと思うが、できない」状態になっています。
この「しなくてはいけない」と思ってしまうのをいったん中断するのが「静養」の一番のポイントなのですが、これが本人には分かりにくいのです。そこで「怠ける試み」を勧めることがあるのです。
もっとも「怠ける」ことを実行するのも簡単でないようです。
うつ状態が悪化しているときは「怠けよう」と試みるゆとりさえなく、「怠けるどころではない」と本人は思ってしまうようです。
またうつ病になる人は元々、生真面目で怠けた体験自体がない人も多いようです。
さらに「怠ける練習なんかしたら人間としてダメになってしまうのでは」と思う人すらいる。
要するに「怠ける試みを勧める」のは、物事を難しく考えてしまう人向けです。「怠ける」体験が豊富な人なら、「そんなの簡単だよ。ただ力を抜いて『面倒くさい』という感覚に浸っていればいいだけさ」と答えるでしょう。このアドバイスに従うのも難しい人は、「どうやったら,少しでも自分が楽と感じるか」を(あくまで試しに)追求しているのだ,という気持で臨んでほしいのです。
これができるようになれば、うつのいちばん悪い時期は過ぎたと思っても構わないでしょう。
「退屈」は回復の目印
私はうつ病の患者さんに対して「怠ける試み」を勧ることがあります。うつが悪化している時期には、怠けること(静養を保つこと、だらだらすること)は治療に有効だと考えるからです。
では、「怠ける試み」はいつまで続けたらいいのでしょうか? まさか一生というわけにはいけないでしょう。
その目安は「退屈感」です。動物全般に言えることだが,どうも人間は、もともと何かをしている方が普通(常態)のようです。健康的な人なら、何もしないでいると、つい退屈になって、何かしらのことをしたくなるものです。
うつ病の人が何もしないでいても、退屈とは感じていないなら,まだ十分回復していない、といえます。逆に退屈だと感じるようになったら、うつの状態から快方に向っていると理解してもよいでしょう。
退屈を感じるようになれば、いつまでも「怠ける試み」を続ける必要はないどころか、無駄に退屈に苦しむだけになるので、今度は退屈しないような行動を取ることを勧めます。
といっても,多くの人はこの段階になったら、人から言われなくても、勝手に何かをやり始めていることが多いものです。
この時期になると、たとえば女性なら化粧や身の回りの片づけ、男性ならテレビやネット、趣味など、さほど努力をしなくても済む何かを再開するという変化が見られることが多いものです。
ちなみに、「退屈」しているかどうかはうつ病と怠け病(こんな言葉は医学用語にはないが)と区別にも応用できます。
うつ病の家族から「本人はうつ病だと言っているのですが、私にはただの怠け病にしか見えないのです。先生はどちらだと思いますか?」といった質問を受けることがあります。何もしていないのに退屈していないなら,それは怠け病ではなく、まだうつが重い状態です。
ただし退屈しているのに何もしないでいる、という状態なら、怠け病と断言できるというわけではありません。
こんな場合、家族は「これではいけない。しっかりしなさい」と注意する前に「退屈なのに、何もしない状態を続けているのはなぜか」を検討した方がよいでしょう。たとえば「やりたいことはあるのだが、失敗が怖いのでやらない」「外出が不安」「いったんやり始めたら、やり過ぎてまた潰れるのでは」といった本人なりの不安や心配があったりするからです。
当クリニックで診ることが多い病気
- 自律神経失調症、身体表現性障害、身体症状性障害
- 〔主な症状〕 めまい、肩凝り、慢性疲労、頭痛、吐き気、更年期症状、動悸など
- うつ病,うつ状態
- 〔主な症状〕 不眠、無気力、意欲減退、食欲不振など
- 過敏性腸症候群(IBS 下痢型、交代型、ガス型)、呑気症
- 〔主な症状〕 腹痛、下痢、便秘、ガス(おなら)、呑気など
- パニック障害、不安障害、空間恐怖
- 〔主な症状〕 動悸、胸痛、息苦しさ、不安など
- 摂食障害(過食症、拒食症
- 〔主な症状〕 低体重、過食、嘔吐など
- その他の病気
- 不眠症、頭痛、線維筋痛症,慢性疼痛、
多汗症、頻尿(神経性頻尿、心因性頻尿)、自臭症、書痙、斜頸、
適応障害、対人緊張(社会不安障害)、人間関係などのストレス、
(お願い)
以下のような精神科の病気は専門外のため扱いません。
統合失調症、躁うつ病、アルコール依存症、てんかん、発達障害など