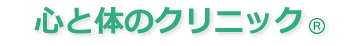読書感想ノート
心療内科
心と体・健康
生き方・思想
心療内科
 『専門医がやさしく教える自律神経失調症』 井出雅弘 (PHP)
『専門医がやさしく教える自律神経失調症』 井出雅弘 (PHP)
クリニック顧問の井出先生監修の本。自律神経失調症がどんな病気であるのかの説明や、病院で行う検査や治療法、ライフスタイルや食事の工夫などについて、タイトル通り「やさしく」書かれている。
おそらく自律神経失調症の解説書のなかでは一番売れた本ではないだろうか。
 『軽症うつ病』 笠原 嘉 (講談社現代新書)
『軽症うつ病』 笠原 嘉 (講談社現代新書)
「ひょっとして自分はうつではないか」と考えた人やうつ病と診断された人、その持つ家族の人がこの本を読むことでうつ病を理解し、どう対処すればよいかのヒントとなる本。
この本は「ひとりでにおこる」軽症のうつ病(内因性うつ病)を念頭に書かれたものである。
軽症うつ病は「ゆううつ気分」「不安感」「おっくう感」の三つが特徴で、周囲の人にも気づかれないほどであるが、これはりっぱな病気であり、抗うつ剤などによる薬物療法が必要であると主張する。
笠原先生はうつ病研究の第一人者であるが、ストレスが原因でうつ状態になっているように見えても、ストレスは単なるきっかけでしかなく実は内因性うつ病であったり、性格が原因によるうつ状態にみえても、慢性型の内因性うつ病である例が多いとする立場に立つ。
 『過敏性腸症候群はここまで治る』 伊藤克人 (主婦と生活社)
『過敏性腸症候群はここまで治る』 伊藤克人 (主婦と生活社)
断定調のタイトルだけから判断して「これを読みさえすれば治るかも」と思う人や逆に「ちょっとうさん臭い本だな」と感じる人もいそうだが、内容はいたって真面目な一般向けの解説書である。診断や治療法の解説のほか、ストレス対処法や食生活の工夫などが分かりやすく紹介してあり、過敏性腸症候群で悩む人や病気を理解しようと思う人のための本といえる。ただし特効薬的なものを期待している人はがっかりするかもしれない。
 『健腸生活のススメ』 辨野 義己 日経プレミアシリーズ
『健腸生活のススメ』 辨野 義己 日経プレミアシリーズ
テレビなどで「腸内細菌によい」とか「善玉菌が増える」などという宣伝をよく目にしますが、本当に健康によいものばかりでもなさそうです。なんと言っても腸内細菌のことはまだ分らないことだらけ、というのが実情でしょう。
この点、著者の辨野義己さんは筋金入りの腸内細菌研究家だけに、データの裏付けがある明快な説明がされています。腸内細菌に関心がある人、過敏性腸症候群で悩んでいる人には勧めたい一冊です。
とくに興味深かったのは自分自身で40日間、肉ばかり食べるという実験をしたという部分です。当初黄色がかっていたウンチは40日たつとタール(黒っぽい油状)のようになり、臭いもきつくなってきた、とのこと。
また当初ウンチは微酸性で、腸内細菌は善玉菌20%悪玉菌10%、日和見菌70%で健康的とされている細菌分布だったが、肉を食べ続けると弱アルカリ性に変化し、また善玉菌は15%に低下、逆に悪玉菌は18%に増加したようです。
この他、腸内細菌とガンを初めとした病気の関係や腸内細菌の状態を良くする工夫、さらにはオナラの話なども出てきます。
 『「やせ願望」の精神病理』 水島広子 (PHP出版)
『「やせ願望」の精神病理』 水島広子 (PHP出版)
筆者は、摂食障害になるのは社会的因子と遺伝因子にストレスが加わるため、と考える。社会的因子とはたとえば「女性はやせている方が美しい」とする画一的な価値観であり、遺伝因子とは新しいものを求めたり、逆に損害を被ることを恐れてしり込みする性格傾向であるとする。
そして摂食障害の治療法として、対人関係療法を提唱している。これは一言でいうと、摂食障害の症状である過食ややせ願望を直接治療するのではなく、摂食障害を治りにくくさせている対人関係というストレスの改善を狙うものである。
「なぜ摂食障害になるのか」や「どうして治りにくいのか」の説明や治療法に関してはさまざまな理論がある。筆者は、人間の性格を7因子にわけるクロニンジャーのモデルを使って摂食障害のメカニズムを説明することを試み、日本ではまだ広まっていない対人関係療法という治療法を摂食障害に応用しようとしている。
私はクロニンジャーのモデルも対人関係療法も詳しくないし、筆者の考えに全面的に賛成するつもりもない。しかし摂食障害のメカニズムや治療法についての説明は明解でうなずける点も多いと考えている。
 『拒食症と過食症 困惑するアリスたち』 山登敬之 (講談社現代新書)
『拒食症と過食症 困惑するアリスたち』 山登敬之 (講談社現代新書)
自分が接した患者さんの言葉を借りて、拒食症や過食症を説明し、どうやったら治るのかを述べている。この本を読めば拒食症や過食症の人の気持ちが理解しやすくなるので、家族が読むにも適しているだろう。
筆者は拒食症や過食症が治る過程を次のように考えている。
それは、
- 少女たちの身体が目を覚ますということ
- 少女たちが自分の言葉で語りはじめるということ
- 自分の親、とくに母と心理的な距離をとろうとすること
- 自分の居場所を探そうとすること
である。
私もこの意見におおむね賛成で、これらが拒食症や過食症が治るための重要な要素だと思う。
 『イメージの病い─モデルとしてのぜんそく』 鈴木秀男 (清水弘文堂)
『イメージの病い─モデルとしてのぜんそく』 鈴木秀男 (清水弘文堂)
喘息に悩む患者さん、とくに自分の病気をどう考えたらよいかに興味を持つ人に勧めたい。
筆者は、喘息を「アレルギー」だけで説明することに反対し、「理由(いわれ)のな い不安」を患者が抱いていることに注目する。そして「理由のない不安」を抱くようになったのは、母性が欠如している母親のもとで乳幼児期を過ごしたからで、そのため「自分は器官が弱い」といったイメージを持ったり「この世界で身体を持って呼吸をし、体温調整をしながら生きる」ことに不安を感じやすいのだ、とする。
筆者の主張はあくまで一つの仮説であり、心療内科で広く認められているものではない。ただし、喘息に限らず「症状が起こるのじゃあないかという不安がよぎったら、実際そうなった」と語る患者さんは心療内科では珍しくない。
私もイメージ(や思いこみ)が病気を長引かせている例はよくあると考えているし、そうした患者さんのなかには乳幼児期の母子関係が歪だった人もいると思う。
したがって、筆者の仮説が妥当かどうかよりも、本を読んだ後で各人が「自分の場合はこの仮説が当てはまるかのだろうか」と検討し、もし当てはまると思ったなら、筆者の提唱するアドバイスに耳を傾けたらよいだろう。
 『 「こころ」はどこで壊れるか──精神医療の虚像と実像』 滝川一廣 (洋泉社)
『 「こころ」はどこで壊れるか──精神医療の虚像と実像』 滝川一廣 (洋泉社)
インタビューの形をとっているので、専門的な部分が多い割には読みやすい。
精神医学や犯罪心理学、思春期問題に興味を持っている人、「ボーダーライン(人格障害)」「ADHD」といった病名で悩んでいる人、「カウンセリング」に過度な期待を持っている人には特に勧めたい。
著者は「こころ」というものはやっかいで不自由なものである。世間でこころを「病む」と表現しているが、それは不自由な「こころ」と自分が「折り合えなくなった」状態のことである。したがって治療の目標は内科や外科のように「悪いところを治す」ではなく「なんとか不自由なこころと折り合いを付ける」ようになることだと考えている。
そして精神失調(病気)は〔性格〕×〔心理社会的環境〕×〔身体や脳〕によって 生じるので、このどれか動きやすいところに働きかければいいと考えている。
筆者の考え方は理論ではなく、治療に長年携わる中で生れたものだと思われる。それは私にとってもうなずける、大いに参考になるものである。
 うつ病九段 先崎学(文藝春秋)
うつ病九段 先崎学(文藝春秋)
一流プロ棋士のうつ病体験記。私がこの本を勧める理由は、典型的なうつ病の経過報告として読めることに加え、「うつ病はどんな経過で良くなっていくか」や「患者本人がどんな工夫をしたらよいか」に関して、大いに参考になるからです。
ただ注意してほしいのは、筆者の場合、これというストレスがないのにうつ状態になったのですが、心療内科の患者さんの大半は仕事や人間関係などのストレスが誘因でうつ状態になっているので、その点は考慮して読むべきでしょう。
簡単に経過を書くと、47歳の誕生日を機に、疲れが取れない、頭が重いという症状が出現。その数日後、朝の4時に目覚めるようになり、日を追うごとに以下のような症状が加わる。
それは将棋を指しても集中できず、思考がまとまらない。対象がない不安に襲われる。外出するといった簡単な決断すらできない。高い所から飛び下りるなど自分の死のイメージが湧く。胸が苦しく呼吸が早くなる、などです。
こうした症状のため入院するのですが、その後の回復の様子も典型的ともいえるもので、入院10日目ぐらいに食事が「ちょっとだけ美味しい」と感じたり「エロ動画がみたい」と思うようになる。しかし外出先の喫茶店でコーヒーをこぼしても、呆然とするだけで店員を呼ぶこともできない。
一ヶ月後に退院してもまだ「退屈」という感覚が持てず、本は眺めるだけで読むことが困難、頭には霧がかかり些細なことでも考えることができない。それでも医者に言われたように「朝食は食べる。生活のリズムを付ける。日中はできるだけ家にはいない」を守り、散歩や図書館、喫茶店などに出かけるのを日課にした。
三ヶ月後に将棋を指したくなり、棋士仲間と指す。内容はボロボロで反則しないのが精一杯だったが、これを機に将棋のごく初歩の問題集を解くところから始めた。
四ヶ月後、棋士仲間と真剣に闘ってときどき勝てるようになる。しかし回復期にありがちな現象に遭遇するようにもなる。それは急に落ち込み物事をネガティブに考えたり、些細なことでも緊張する、夜中に目覚めてしまうなどである。それでもこの頃には「退屈」感じたり本も読めるようになった。
まだ「感性」が完全に戻っていないと感じているようだが、九ヶ月後に正式復帰する運びとなる。おそらく本当の回復はそれからなのであろう。
心と体、健康
 『健康食品ノート』 瀬川至朗 (岩波新書)
『健康食品ノート』 瀬川至朗 (岩波新書)
この本は筆者が毎日新聞に連載した記事を加筆したものである。健康食品とは何かに始まり、イチョウ葉エキスやプロポリスなどお馴染みの健康食品を検証している。
またダイエット食品や、ガンを治せるかという興味ある話題も提供する。
全編を通じて、できるだけ科学的かつ客観的に今、話題のさまざまな健康食品をとりあげ、健康食品との付き合い方をを解説している。
 『「赤本」の世界』 山崎光夫 (文春新書)
『「赤本」の世界』 山崎光夫 (文春新書)
築田多吉の「赤本」は大正14年の出版以来、1000万部以上が出版されている本である。赤本の内容は病気治療や健康法、応急処置、不老長寿術、死体の処置など多岐にわたる。また自らが発明した梅肉エキスや卵油の作り方も本のなかで公開している。
「赤本の世界」は「赤本」のエッセンスを紹介したものである。
これを読むと、多吉にとっては「健康道」とでもいうべき生き方があって、それを踏まえたうえで一つ一つの健康法や治療法があると考えていることがわかる。
この点が、通常の健康書や病気本との大きな違いだろう。また最近は、数多ある自然食品や健康グッズを適切に選びさえすれば、自分の健康が得られると勘違いしている人を見かけるが、こんな風潮に警鐘を鳴らす本でもある。
 『健康病 健康社会はわれわれを不幸にする』 上杉正幸 (洋泉社)
『健康病 健康社会はわれわれを不幸にする』 上杉正幸 (洋泉社)
さまざまなデータによると、日本人は生活の中で「最も大切なものは健康」だと考える一方で「自分の健康に対して不安を感じている」人が多い。この矛盾がどうして生じたのかについて筆者は考察している。
たとえば、その理由として、筆者はガンをはじめとする成人病が疾病構造の中で大きな比重を占めるようになった結果、早期発見や早期治療の重要が強調されるようになった現状を指摘している。早期発見の考え方は、自分は健康だと思っている人でもひそかに病状が進行していることを前提としている。また、人間ドッグなどを行ってもあくまで今回、結果した範囲では異常がなかった、という報告でしかなく、将来に病気にならないという保証をしてくれるわけではない。
たしかにそれでは、人はいつも病気になるに不安を抱えることになる。筆者はこの矛盾の解決法として「異常がない健康」を目標にするのではなく、「生きがい」を目的とすべきであり、健康は「生きがい」のための一つの条件でしかないと説く。
 『「心」はからだの外にある』 河野 哲也 (NHKブックス)
『「心」はからだの外にある』 河野 哲也 (NHKブックス)
私には難解に思える部分が随所にあるが、それでも紹介したいと思ったのは、この本が「自分」というものを重視する心理主義を痛烈に批判しているからである。現代は本来なら環境や社会にその原因を求めるべきことでも、心理的原因に求める傾向がある。たとえばニートの問題を、その人の怠惰ややる気のなさに求め、その人を取り巻く社会環境の要因を軽視していると説明する。著者は生態学的心理学者J・ギブソンにヒントを得て、自分を取り巻く環境に働きかけることで「自分が充実して生きられる環境」を自ら造り出す重要性を説く。
「自分探し」を心理学を学ぶことに求める人をみかけることは少なくないが、「環境に働きかける」ことも自分探しになるという発想を持つことは大切だろう。
 『身体感覚を取り戻す─腰・肚文化の再生』 斎藤 孝 (NHKブックス)
『身体感覚を取り戻す─腰・肚文化の再生』 斎藤 孝 (NHKブックス)
この本の冒頭で、筆者は次のような問題提起をしている。
〔最近、自己の存在感の希薄化がしばしば問題にされる。自分がしっかりここに存在していると感じられるためには、心理面だけでなく、身体感覚の助けも必要である。現在の日本で自分のからだに一本しっかりと背筋が通っていると言うことができる者はどれだけいるであろうか。〕
そうなったのは、かっての日本にあった「腰を据える」や「肚を決める」などの「 腰吐文化」が喪失したことと関係あると訴えている。
そして、自然体で立つ、歩く、座るなどの基本的動作の重要性を説き、また「練る、磨く、研ぐ、絞める、絞る、背負う」などの体の動きを表現する言葉が使われなくなっている現状や、型を身につけるという発想の意義を強調している。
私も身体感覚の重要性を実感している。私たちは、つい感情や考えなどの「心」が「体」とは独立してあるような錯覚を持ちやすいが、「心」は「体」の支えがあって初めてしっかりしたものとなる。たとえば他人の話を聞いたとき、話の内容自体には賛同できても、その当人の態度が「そわそわしている」「おどおどしている」と感じると、信用する気にならないだろう。また、いくら「朝起きたら、こんなことをしよう」と思っていても、朝だるくて仕方がないとその気も失せてしまうものである。
したがって、身体感覚を養うことには大賛成である。ただし、身体感覚を養うには腰肚文化の習得以外の方法もあること、そして腰肚文化の習得はけっして簡単ではないことも付記しておく。
 『マインドフルネス認知療法─うつを予防する新しいアプローチ』 Z.N.シーガル (北大路書房)
『マインドフルネス認知療法─うつを予防する新しいアプローチ』 Z.N.シーガル (北大路書房)
本書は、うつ病に対してマインドフルネスを利用した認知療法的アプローチがうつ病とくに、うつ病の再発防止に有効だとするもものである。
マインドフルネスは仏教の瞑想法の一つで「心に浮かぶ思考や感情に対して、そのまま従ったり価値判断をせず、ただその思考や感情と距離をとって観察する」ものである。マインドフルネス認知療法はこれを利用してうつ病の際に現れやすいネガティブな思考の繰り返し(自動思考、思考の反芻)が起きないようにする。
やり方自体は決して難しくないし、本書を読むことで独習も可能である。しかし体験してみるとわかるが、マインドフルネスの状態を持続させるのは容易ではない。(ちなみに筆者自身も、マインドフルネスの実践経験はほとんどない!)。
このためどの程度お勧めしてよいか分からない。ただしうつ病はネガティブな思考を伴いやすいが、思考を変えるのではなく、その思考と距離を取ることが、うつ病の治療や予防になるという主張は、私も正しいと考えている。
以下、要約
うつ病になっているときはネガティブな思考になりやすい。認知療法の創始者であるベックはネガティブな思考そのものがうつの誘因であり、うつを持続させる要因になると考え、根拠のないネガティブな思考(非機能的思考)を気づき、修正する方法として認知療法を提唱した。
その後の調査研究で、うつ病治療として認知療法は効果があることが分かった。このことを踏まえ、筆者は認知療法はうつ病予防の方法にも役立てようという方針を立て、先ずどんな人がうつを再発しやすいのかについて検討した。当初、ネガティブな思考など非機能的(合理的でない)信念や態度を持っている人が再発しやすいと考えた。しかしアンケートでは、非機能的な考えは「うつが治った人」と「うつ病になったことがない人」とで差がなかった。
これでは認知療法はうつ病予防の方法には役立たないということなり、筆者らは方針変更を余儀なくされた。
次に以下のことに注目した。それは健康な人でも「気分の落ち込みがネガティブな思考を引き起こす」ことは知られているが、うつ経験者はその程度かひどく、気分の落ち込みがネガティブな思考を活性化させる(抑うつ的処理活性仮説)という研究報告や、うつ「気分攻撃」によって非機能的態度が増加しやすい患者はうつが再発しやすい傾向にあるという報告である。
以上から、ささいな気分の変化によってネガティブな思考を活性化されやすい傾向こそがうつの予防のために取り組むべき課題だと考えた。認知療法が何故効果あるのかという疑問に対し、当初はネガティブ思考の内容を変化させるからだ、と考えられていた。しかし、ネガティブな思考が生じたとき、 それをチェックしたり内容を評価をするため、その思考から離れることを繰り返したりするなかで、ネガティブな思考と感情と「距離を取る」あるいは「脱中心化」するからだという説も提出された。
筆者は、じつはそれこそ中心ではないかと考え、ネガティブな思考と距離を置くような思考を教育する方法としてマインドフルネスに着目し、マインドフルネス認知療法を開発した。
参考)ベックの認知療法
認知療法は、よぎった考えを「捕まえる」ように励まし、何がどんな風に考えているのかを検討する。そして活動スケジューリング、達成感と楽しさの評価、思考のモニタリングや論駁、認知的リハーサル、他の考え方を検討すること、非機能的態度への気づきや対処、などを身につける技法である。
 『生物と無生物のあいだ』
福岡伸一 ( 講談社現代新書)
『生物と無生物のあいだ』
福岡伸一 ( 講談社現代新書)
筆者は分子生物学者で多くの著作がある。動的平衡という概念を提唱したこの本は56万部を越えるベストセラーとなった。
筆者は、生命は精巧なパーツからなるプラモデルとは違うという主張をする。その例として遺伝子欠損を挙げる。遺伝子はいわば私たちの体の設計図である。遺伝子の一部が欠けると、産まれた体は当然不完全なものとなる。もしその部分が生命にとって重要なものなら、大きな支障を来す病気となる。
遺伝子の一部が欠けると、プラモデルの部品が欠けるように、その部分は不完全なものになる、というのは医学においても常識である。ところが筆者は自身がかかわった次のような実験では不思議な現象が起きた。膵臓はインシュリンや酵素を作るが、この酵素産生に大きな役割をしていると思われる部分を遺伝子レベルで完全に無くしたマウス(ノックアウトマウス)を作ってみた。そしてどんな障害が生まれるか観察した。ところが糖尿病などになることもなく、何の支障も見られなかったというものである。
筆者はこの不思議な現象こそ生命とプラモデルとが違う点であり、生命には自動的に足りない部分を他の方法で補おうとする働きがあるからだとし、これを動的平衡という概念で説明している。
生命体は静止して見えても常に動いて一種の平衡状態を保っている。この例としてネズミに3日間だけ、重窒素で目印をつけたアミノ酸を含んだ食べ物を与えるという実験を紹介している。この3日間において、目印をつけたアミノ酸は尿や便として3割だけが排泄され、全体の半分以上は腸壁や腎臓、肝臓などを含む身体のあらゆる部分(タンパクとして)に取り込まれていた。その一方で体重は変わらなかった。つまりネズミは以前と変わらないように見えるが、たった3日間でそのネズミを構成しているタンパクは半分以上が新たに作り出され、同量のタンパクが分解され、排出されたということである。(P158)。
固定的に見える歯や骨、体脂肪でも、もちろん脳や神経においても、命がある限り絶え間のない合成と分解がなされる。こうした指摘は私たちに新しい生命観を与えてくれるに違いない。たとえば私は以前から変わらない私があるように思っているが、それは私の勘違いで、少し前の私と今の私は中身がすっかり変わっている。そうした見方をするだけで、以前とは違う方向に目を向く気持になるのは私の錯覚だろうか。
 『腰痛探検家』 髙野秀行 (集英社文庫)
『腰痛探検家』 髙野秀行 (集英社文庫)
腰痛で長く悩む人には一読の価値あり。
それまでもときどき腰痛に悩むことはあったが、40歳のときに立ったり歩いたりするだけで痛むようになる。やむなく知人の勧めや評判を頼りに、何カ所もの整骨院や整体院、鍼灸院、整形外科などを巡ることになる。
ところが向に良くならないだけでなく、そのつど説明も違う。整形外科だけでも椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、先天性臼蓋形成不全といった病名が付けられる。
最後にたどり着いた整形外科では、股関節や腰椎には異常がないと言われ、ついに心療内科を受診することになる。しかし抗うつ剤の副作用に苦しむだけで改善の兆しがみられない。
ついには「もうどうなってもいい。薬も治療も止めよう」という気持で区民プールで泳ぎ始めるが、これが意外な効果をみせ、腰痛持ちであること忘れるほど改善する。
筆者なり結論として、なかなか改善しなかったのは「腰が痛い」「早く治さなきゃ」とい考えに取りつかれてしまったからで、「治そうと思わない」状態に変化したので改善した、としている。
全ての人に当てはまるとは思わないが「なかなか改善しない」と日々悩んでいる人には参考になるのではないか。
それにしても「ただならぬ情熱と時間をかけても報われることなく、ついには半ばな自暴自棄になって試みる行為が望外の良い結果に」といった話はさまざまな人生の転機や発明発見の体験談でよく耳にする。
私はそこには共通する何かがあるのだろうと、よく考えるのだが、あいにくまだ結論に至っていない。
生き方、思想
 子育ての大誤解―重要なのは親じゃない ジュディス・リッチ・ハリス ハヤカワ文庫NF
子育ての大誤解―重要なのは親じゃない ジュディス・リッチ・ハリス ハヤカワ文庫NF
母親という役割を担っている女性で「子供が学校や社会で適応できないのは、私の育て方が悪かったから」と悲観的になっている人を見かけることは珍しくない。筆者は「子供がどう育つかは親次第」といった「子育て神話」を強く否定し、以下のような主張をする。
1 性格の半分は遺伝、残りの半分は環境で決まる。
2 環境要因として、性格形成に大きな影響を与えるのは、親との家庭環境や教育ではなく、子供時代に過ごす子供集団などである。
またこれに付随して以下のようにも述べている。
3 親ができるの衣食住の安定供給および環境の準備。これらは子供の性格形成に直接は関係しないが、招来的な健康や職業的な成功には大きく影響する。
4 子供は同じ親から生まれても一人一人違う。よって子育てにマニュアルはない。
5 子供は本能的に自分に似たもの同士で集団を作り、その集団と自分を同一視し、その集団の規範を身につける。こうして性格が形成される(集団社会化説)。
子育てに悩んでいる母親、子供時代の親との関係のため、人生に行き詰まっていると考えている人、自分の性格を変えたいと思っている人、などには一読する価値があるだろう。
 『サピエンス全史』 ユヴァル・ノア・ハラリ (河出書房新社)
『サピエンス全史』 ユヴァル・ノア・ハラリ (河出書房新社)
世界で1200万部も出版されたベストセラー。通常の歴史書が、文明の始まりから現代までで終わるのに対し、この本は私たちホモ・サピエンスの誕生以前から始まり、未来までを語る。それだけでなく認知革命、農業革命、科学革命という大きな変革をキーワードに、私たちに「幸福とは何か」を語りかける点が比類ない。
・認知革命──私たちが地球の支配者になれた理由
認知革命とは七万年前に始まる「フィクションを共同で信じる能力」によって生じた変革を指す。この能力を獲得したので、私たちは見知らぬ同士との協力が可能となり、ネアンデルタール人などとの競争にも打ち勝ち、現代の繁栄をもたらしたというのが、本書全体に流れる大きなテーマである。
「フィクションを共同で信じる能力」の一例として、お札(貨幣)がある。お札はただの紙切れだが、自分の欲しい物と交換できると皆が信じているので価値が生れる。宗教や会社や国家、法律、主義、文化などが存在できるのもこの能力のためである。しかし、私たちはこの想像上の秩序の中に閉じ込められることにもなっている。
・農業革命──楽を求めたので苦しむ?
約1万2000年前、気候の安定化に伴い農耕生活が始まった。そうなったのは安定した収穫が見込め、より快適な生活が望めたからだろうが、実際はそうならなかった。それというのも、定住と食料供給の増加により人口が増え、結果として人々は以前に増して労働を強いられた。また農地や穀倉を守る必要が生じ、争いも増えた。
ハラリは「人々はなぜ、こうした計算違いをしたのか」と問いかけ「それは人は自ら下す決定の全貌を捉えきれないからだ」とする。
より快適な暮らしを求めることが、新たな苦難を呼び込むことは、よくある。たとえば早期退職したいと懸命に働いても、その年齢になったときはローンや子供を抱え、車やバカンスも必要と考え、さらに一生懸命働くことになりかねない。
この例でも分かるが、歴史の数少ない鉄則に「贅沢品は必需品となり、新たな義務を生じる」というのがあり、より快適な生活の探求は、想像もしなかった形に世界を変える、と述べる。
・科学革命──無知の自覚が発展に
科学革命は近代科学による変革で500年前に始まる。近代科学には、次のような特色がある。先ず、進んで無知を認める態度である。それまで、重要なことはキリスト教や仏教の教典などに全て書かれているとされていたが、新大陸の存在など、まだ未知の存在を認めるように変化した。
次に、新しい知識獲得の手段として観察と実証を中心にした。さらにテクノロジー(科学技術や工学技術)を駆使して、単なる知識に留めず有用な力に活用する。
これを権力拡大を願う帝国主義と、経済成長を善とする資本主義が後押しすることで、兵器・医薬・機械の開発が進み、生産や消費が爆発的に向上した。
ただしこれに伴い、地域コミュニティと家族は崩壊していく。元々、私たちは親密な小規模コミュニティの中で家族と共に暮らしていた。これは認知革命や農業革命の後でも変わらず、家族は福祉や医療、教育をも担い、家族では手がおえないときはコミュニテイが助け舟を出した。しかし僅か二世紀の間に、こうした役割は国家や市場の手に移り、人々は「個人になる」ように仕向けられた。
地域コミュニティや家族の代わりに、国民や消費者という想像上のコミュニティが提供された。こうした制度だけでなく個人の心も変革を強いられた。もっとも想像上のコミュニティは嘘(フェイク)ではなく、認知革命の産物である想像(共同主観的現実)である。これは集合的想像の中にしか存在しないがその力は絶大だ。
ハラリは別のところで次のように述べている。「歴史を研究するのは、未来を知るためではなく、視野を拡げ、現在の私たちの状況は自然なものでも必然的なものでもなく、したがって私たちの前には、想像しているよりもずっと多くの可能性があることを理解するためなのだ」、と。
 『 転機の心理学』 杉浦健 (ナカニシヤ出版)
『 転機の心理学』 杉浦健 (ナカニシヤ出版)
人はときに大きく変わるときがある。そんなときその人の中ではどんな変化が生じているのだろうか。これがこの本のテーマである。転機を体験した人の話や闘病記、成功談などを見聞きすると、不思議なほど共通点がある。それは、いよいよ行き詰まったと思えるとき、ささいな出来事がきったけとなり、その後の大きな変化を生むというものだ。筆者はこうした研究を試み、転機のプロセスを以下のようにまとめた。
もちろん転機があった人すべてが同じプロセスを辿るとは思わないが、こうしたプロセスを想定することは、病気に悩む人にとっても、また自分の生き方に疑問を募らせている人にとっても有益だろう。
1 始まり:始まりは何かが終わるとき
筆者はブリッジズの「『終わり』は何かがうまくいかなくなるときから始まる」という言葉を引用している。また転機のプロセスには「変わりたいという動機づけ」が必要とも述べている。
2 空白の期間
転機のプロセスにおいて、何らかの空白もしくは無為の時期がある。高橋は古い解釈を捨て、新しい解釈を生み出すまでの過渡期ととらえている。
3 空白期間における屈曲点
空白期間がある程度経つと「次第に何かをしなくては」といった前向きなエネルギーが湧いてくる。
4 変わるとき、変わる瞬間
「変わる瞬間」はしばしば意識状態が低下しているとき生じる。
5 転機の語り
本当に変わったと確信するためには、変わったことが確認されるための時間や、それを確認する心の中の作業が必要。
 『インナー・ゲーム』 W.T.ガルウエイ (日刊スボーツ出版社)
『インナー・ゲーム』 W.T.ガルウエイ (日刊スボーツ出版社)
この本は直接的には「努力してもテニスが上達しない人」を対象に書かれたテニスの教本であるが、アメリカではミリオンセラーとなった。それはテニス以外のさまざな分野で役立つからである。筆者の主張は一言でいうと「考えることを止め、見たり感じたりすることを重視する」ことの勧めである。
たとえば「サーブにおける自分の欠点はラケットの位置が低いことだ」と頭では理解してもできない人がいる。また「ここで負けたら、恥をかいてしまう」と考えることで、焦りを呼びせっかくの力が発揮できない人がいる。
こうした人に必要なものは、頭で考えて自分の体に命令することをやめ、ボールの行方をじっくり見たり、自分の体の感覚に注目することだとする。
私自身はテニスをやらないが、私にもこの本は役立つと思った。それは「どうすればよいか」が分かっていても、焦りや緊張、嗜癖(くせ)のためできない、という問題に取り組むヒントが書いてあるからである。
 『もう一つの人間観』 和田重正 (地湧社)
『もう一つの人間観』 和田重正 (地湧社)
この本は氏が十七歳から五十年間、一途に温めてきた「この自分とは何だろう」「人はどう生きたらいいのか」という課題の自分なりの答案であるという。この疑問に対して、自分はヒトという種に属する一個体だと見なすところから考えている。
自分が生きているということは食べたいとか、行きたいなど「~したい」という欲望に駆られてのことであり、こうした欲望が満たされないときに苦悩は生じる。この苦悩は人間に大脳があることにでいっそう深刻になると氏は考える。
大脳があると、たとえば食欲や性欲などの本能は、財欲や支配欲、名誉欲など、自己中心的な形で発展し、満たされることのない苦悩が生まれる。さらに大脳が発達した個体が集まる人間社会は、他の生物社会よりもいごこちが悪くなり、苦しむことになる。
このように氏は人間のあり方に対してきわめて悲観的な見解を述べる。しかし氏の主張のユニークな点はここからである。氏は、そうなると人間は必然的に苦悩の原因を考えることになる。この地球に単細胞生物が誕生し、人間へと発展してきたのは、たんなる偶然の積み重ねではない。なにか、人間を含めた生物を生きさせようとする力があり、それ(氏は「いのち」とよぶ)は「自分とはなにか」を明らかに知っている生物(人間)を地上に実現しようとしているのではないか、という仮説を立てる。
その上で苦悩の解決法は、大脳が苦悩を解決する方法を持っていないとはっきり自覚し、「いのち」に従うことだとする。
氏の主張に対して反論することは簡単である。たとえば「人間に本能があると主張すること自体がすでに非科学的だ」「『いのち』という仮説は全く根拠がない」などである。しかし、私のみならず「苦悩を解決しようと大脳を駆使しているが、結果として大脳はむしろ苦悩を増やしているのではないか」という疑問を持つ人は少なくないだろう。またこの地球が太古から現在、未来に向かって、なんらかの方向を持って発展しているのではないかという推測は、あながち的外れではないと私も思っている。
 『脳はなぜ心を作ったのか』 前野 隆司 (筑摩書房)
『脳はなぜ心を作ったのか』 前野 隆司 (筑摩書房)
この本において筆者は「受動意識仮説」なるものを提唱している。これは意識としての「私」は私を統括しているように思っているが、それは錯覚であり、「私」はせいぜい起こっていることを受動的に眺めているだけに過ぎないとする主張である。
そんな話を聞くと、トンデモ本のように思ってしまうが、この主張は筆者の専門であるロボットの心を研究する過程で生まれたものである。筆者は哲学者や認知科学者が心に対して「心とはだいたいこんな物だが、核心のところはまだわからない、とか複雑すぎてすぐには作れない」という煮え切らないものばかりだった。これに対して私の考え方によれば、心が実に単純なメカニズムできていて、作ることすら簡単であることを誰にでもわかる形で明示できる」とする。
そしてその主張に沿う形で、心の要素とされる知、情、意(意図)、記憶と学習、意識の五つを順に、それが自分の意志というより無意識的な働きによって成り立っていることを解説していく。
たとえば「意図」については、リベット(1975年)の研究を紹介している。リベットの研究は一言でいうと、自分が指を曲げようと意図するよりも0.35秒前に脳内ではその運動に対する運動準備電位が変化している。つまり考えるよりも先に脳は指を曲げるための指示を出しているという実験結果の報告である。
このような解説の後、筆者は意識としての「私」は世界の隅っこにいて、無数の小びとたち(無意識)の結果を受け取るだけの脇役である。「私」は外的な世界とつながってさえいないで、ただ小びとたちが教えてくれたことを通して世界のことを知る監獄の中の囚人である、とする。
では、私(意識)は何のために存在するのかというと、それはエピソード記憶のためであるとする。エピソード記憶とは時間や場所、そのときの感情を含む体験としての記憶のことである。
これが意識とどう関係あるかというと、私たちの脳には容量に限界があるので、自分の体験を要約して記憶する必要があり、そのために必要十分なものが「意識」である。つまり意識はエピソード記憶することの必然性から進化的に生じたのだとする。
本を読んでいく中で「こじつけではないか」という疑問が出るかもしれないが、こうした主張は最先端の脳科学研究の考えとも矛盾しない内容である。私とは何か、や脳の仕組みについて興味を持つ人には一読を勧めたい。